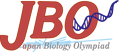ニュース カテゴリの記事
立命館慶祥中学校・高等学校 主催「数理・科学チャレンジ サマーキャンプ2018」において、JBO運営委員が下の日程および内容で、講座を担当しました。
日程: 2018年8月7日(火)~8月9日(木)
場所: 立命館慶祥中学校・高等学校
担当者: JBO運営委員 谷津潤 森長真一
| 1日目 | ||||
| 14:00〜15:30 | 講義1 | 谷津 | 分子生物学 | 制限酵素の説明と実験 |
| 15:50〜17:20 | 講義2 | 共同活動 | 特定のテーマについて共同で課題解決 | |
| 2日目 | ||||
| 9:00〜10:30 | 講義3 | 森長 | 生物の適応 | 生物に見られる適応の具体的事例とトレードオフの演習 |
| 10:50〜12:20 | 講義4 | 谷津 | 発生学 | ショウジョウバエの個体と生殖巣の観察 |
| 12:20〜14:00 | 昼食と自主活動 | 講義の宿題や課題に取り組む | ||
| 14:00〜15:30 | 講義5 | 谷津 | 発生学 | ショウジョウバエの胚の観察 |
| 分子生物学 | 制限酵素を使用した実験結果の考察 | |||
| 15:50〜17:20 | 講義6 | 森長 | 利他行動と社会性 | 動物にみられる利他行動・社会性の説明と血縁度計算の演習 |
| 3日目 | ||||
| 9:00〜10:30 | 講義7 | 森長 | 発生と進化 | 形態進化に関与する遺伝子の役割と盲斑検出の演習 |


日本生物学オリンピック2018 予選が全国の会場で 2018/7/15(日) に実施されました。
4,189名(女性:2,311名、男性:1,878名)が日本生物学オリンピック2018予選に挑戦しました。
ニュース, 日本生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック2018
参加申込:2018年4月1日(日)~ 5月31日(木)
予選日時:2018年7月15日(日)13:30-15:00
予選会場:全国約100箇所の大学や高等学校
参加費:無料
2018年3月24日土曜日に岡山大学を会場として、県内中学生・高校生の化学と生物学希望者に対して午前に全体会を10時から2時間、午後は分科会として3時間の説明等をしました。
午前の部では、開会行事の後に50分間で国内予選・国際大会についての説明を行い、また出題される内容と大学進学後の勉強との相関についても説明しました。最後に日本代表への道と題して、過去に指導した生徒の事も含めて説明しました。
午後は、生物分科会として生物学オリンピックを目指す生徒対象として、幾つかの内容に関して説明しました。参加生徒は54名の予定でしたが、4人が欠席しましたが午前中の全体会に参加した生徒の中から、2名が生物分科会に急遽参加しました。僅かな時間で過去問の解説をするよりも、生き物に関する興味を引き出す事が大切だと考え、身近な植物の種子繁殖に関して、概説説明と持ち込んだ種子の観察を通して理解を図りました。持参した種子は風散布種子としてアルソミトラ・シラカンバ・ウバユリの翼果、毛羽を持つガガイモ、小型軽量のモジズリ・ヤセウツボ、構造的風散布種子のナガミヒナゲシの種子散布について考察しました。写真としてフタバガキ・シナノキ・セイヨウタンポポを提示しました。動物散布種子として「引っ付き虫」であるアメリカセンダングサ・コセンダングサ・ヌスビトハギを、貯食種子としてオニグルミを、また写真でガマズミ・クスノキ・ヤドリギ・ホザキヤドリギ・オオオナモミ・チカラシバ・メナモミ・チヂミザサ・ライオンゴロシ(デビルクロー)を提示しました。水散布種子としては写真のみの提示で、オヒルギの胎生種子とエンタダマメ(モダマ)を提示しました。重力散布種子は、果樹としてのリンゴ・ナシについて考察し、また蔓植物の例についても説明しました。最後に自動種子と名付けたカラスムギを持参して、濡らす事で芒が動く事を観察させました。
続いて心臓の位置と、誤解を受ける理由として、左右の心室が拍動の際に血液を送り出す圧力について説明をしました。魚類の一心房一心室の合理性と、陸上化による進化の過程を考察しました。腎臓ではヘンレのループの機能であるアクアポリンと、塩類チャネルの分布について説明し、また皮質から髄質にかけての濃度勾配についても説明しました。
最後に、石井が過去に指導して代表として送り出した生徒に対する指導に関する詳細を語り、全ての締めくくりとしました。
生徒は実に熱心に話を聞き、じっくりと観察し、様々なことについて考察を行いました。とても良い雰囲気の中、講義が進められたことと、生徒たちが集中して参加することができたことから、生徒たちの意識の高さと能力の高さを感じました。(文責 石井規雄)



今回の講座(2017年12月26日(火)〜 28日(木)は、90分9講座でしたので、遺伝子を中心に据えて生物の講義と観察を実施した。
一時間目は、導入として人体の臓器に触れ、その位置や働きについての説明をした。特に腎臓では、髄質における濃度勾配とヘンレのループの機能を中心に説明した。それから遺伝子としてのDNA研究史の概略を解説し、遺伝子を運搬する配偶子について説明し、減数分裂の教科書に書かれてない最も重要な意義について説明した。
二時間目は、持参したツバキの葉の切片作製法を説明し、実習として各自が作成し、スケッチを書くことの意味と意義が分かれば、光学顕微鏡の使い方は概ね理解できることを指導した。
三時間目は、今回参加した数学オリンピック・物理学オリンピック・化学オリンピック・生物学オリンピック・地学オリンピックの共同作業として、「種子の繁殖戦略」の解析を実施した。風散布種子・動物散布種子・水散布種子・重力散布種子・自動種子について石井が概説し、その後生徒による解析と発表が行われた。
四時間目は、真花説を基として、様々な果実を観察して、形成している子房の室数を考察し、元々は葉が変化したものであることから、1枚の葉由来・2枚の葉由来・3枚の葉由来・4枚の葉由来・5枚の葉由来・多数の葉由来を実際に観察して、ミカンの食用部分が葉のどの部分に該当するかを、ツバキの葉の切片と対比させた。
五時間目は、植物の花粉媒介戦略として、風媒花・動物媒花・水媒花を説明し閉鎖花についても説明した。
六時間目は、種子の繁殖戦略について、実際に観察し説明をした。様々な種子の殆どは媒体によって種子を移動させることが分かっており、風を利用する場合に翼を持つもの・小型軽量のもの・毛羽などを持つもの・特殊な器官を利用して効率よく種子散布するものなど多彩であることを理解させた。動物散布に関しては、「ひっつき虫図鑑」が発刊されるくらいにユニークなものがあることも説明した。
七、八時間目は、PCRについて、原理の説明、実験指導および演習問題の解説を行った。まず、生徒らにマイクロピペッターの操作に慣れてもらった後、サンプル調製を行わせ、PCR反応を行った。次に、PCR産物が増幅するまでの待ち時間を利用して、実験結果の予想を立ててもらい、さらに、PCRの原理を正しく理解させることを目的として作成した演習問題を解いてもらった。最後に、PCR産物に対してアガロースゲル電気泳動を行った。
九時間目は、まとめ・国際生物学オリンピック・その他について説明し、特に国際生物学オリンピックに関しては、目的・歴史・日本が参加してからの状況・生徒を指導した実践経過について説明をした。(文責:石井規雄・谷津潤)

ニュース, 国際生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック, 関連する催し
都市の微生物と市民の健康
生物学オリンピックOBの石田晴輝・佐藤紀胤さん(東京大学2年)は慶応義塾大学・上智大学の学部生といっしょに研究チームGoSWABで活動しています。公共交通機関など都市環境での微生物生態系やヒトの遺伝子をメタゲノム解析して、環境と生物の関係を探っています。募集期間:2018年4月11日までのクラウドファンディングで、東京都内の駅での微生物生態系の大規模かつ詳細な解析への支援を希望しています。
京大生チャレンジコンテストに挑戦
JBO2014に出場し本選において銅賞を獲得し、日本代表候補となった司悠真さん(現在 京都大学理学部在学)の参加する理学部の5名のチームが「脳でオーロラは聞こえるか」という研究プロジェクトの研究費を 京都大学の支援の元 クラウドファンディングによって集めようとしています。「京大生チャレンジコンテスト(SPEC:Student Projects for Enhancing Creativity)」のページをごらんください。 寄付募集期間は2018年1月31日までです。
ガーナ生物学チャレンジへの貢献
IBO2012シンガポール大会日本代表の荒木大河さんが ガーナ生物学チャレンジをコーディネータとして組織し 大きな貢献をしました。 ガーナ生物学チャレンジは2016年5月にガーナ大学において成功裏に実施されました。大会ではJBOの問題をもとに作られた筆記試験が実施され、さらに参加者はガーナ大学での電気泳動体験セッションに参加しました。将来は国際生物学オリンピックへの参加を目指しているとのことです。
学術クラウドファンディングに挑戦
IBO2014インドネシア大会日本代表の那須田桂さんらの学生チームが、合成生物学の国際大会であるiGEMに「細胞分裂で色が変わる大腸菌を作りたい!」というテーマで参加を目指しています。iGEM参加のための費用を学術クラウドファンディングにより調達しました。 (達成率174%)
なおiGEMには IBO2007カナダ大会日本代表の本多健太郎さんはじめ 下のリストにしめすように多くのOBOGが参加してきています。iGEMは学生の国際的なコンテストであるばかりでなく、合成生物学のライブラリであるBioBrickに貢献していることでも注目されています。
UT−Tokyo チーム
2010 仮屋園遼、本多健太郎
2011 泉貴人、海老沼五百理、濱崎真夏
2012 海老沼五百理、大塚祐太、水口智仁
2013 海老沼五百理、大塚祐太、水口智仁
2014 中村絢斗
2015 中村絢斗、那須田桂
2016 那須田桂、真田兼行
Oxford iGEM
2016 石田秀

国際生物学オリンピック(IBO)の創設に関わり、それ以降、27年間、IBO運営の中心人物として活躍されてきたチェコ共和国のTomáš Soukup氏がご逝去されました。彼は、2016年2月25日の夜、研究所からの帰宅途中、プラハ市内の横断歩道を青信号時に横断中のところ、酒酔い運転の車にはねられ、頭部に大けがを負われました。その後、意識が戻らないまま入院治療を続けてこられましたが、さる2017年7月29日、プラハ市内の病院にてご逝去されました。まさにその日はイギリスの University of Warwick で開かれた第28回IBOの閉会式の日でした。同年、8月9日葬儀がプラハで執り行われ、IBOからは Steering Committee の Gerard Cobut 委員(ベルギー)が参列し、弔辞を述べました。
Tomáš Soukup氏は骨格筋の生理学の権威で、チェコ国立科学アカデミー 生理学研究所で長年、骨格筋の成長とファイバータイプの制御に関する研究を続けてこられました。2009年に開かれた IBO筑波大会の後も、すぐに京都で開催中の第36回国際生理学会世界大会に出席、研究発表をされるなど、IBOの運営を一手に引き受けながらも、筋肉生理学の第一線で活躍してこられました。
Tomáš Soukup氏は IBO大会や IBO Advisory Meeting においても指導的役割を果たしてこられ、その温かい包容力と人柄はまさに IBO の魂的存在でした。ここに深く哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
国際生物学オリンピック(IBO)日本委員会
2017年4月30日に、佐賀県で唯一理数科を持つ佐賀県立致遠館高等学校にて、生物学オリンピック合同学習会を実施しました。午前の部は生徒に対しての学習会で、致遠館高校が行っているSSHの一環として他校にも案内をして行われました。参加生徒は6名で、全員が致遠館の生徒でした。

内容として初めにIBOの紹介をしました。特に参加する意義として、多くの知識を持つ事が必要である事や、実験技術の基礎を身につける必要、更に様々な知識を総動員して考察する楽しさを予め体験しておく等は、将来の研究者を目指す際の必要不可欠な要素であり、オリンピックはあくまでも通過点である事を説明しました。そして、国内大会で顔を合わせる全国の生徒との交流は、生物好きの集まりであること、国際大会では世界の生徒との交流があること等を話しました。次に過去問に触れ、見方を変えることで解答に近づくことを説明しました。生態学的な考察問題として、カラスムギの種子を見せました。初めに乾燥標本をそのままの状態で見せましたが、当然面白さに気づく生徒はいませんでしたが、次に水を含ませて生徒に見せると、いきなり動き出しますからその面白さに釘付けになりました。また佐賀県内でも見られるナガミヒナゲシの繁殖戦略について、昨年採集した乾燥標本を見せて、種子の散布形態の考察を行いました。最後に実技指導として、ツバキの葉の切片作成について体験をしてもらいました。通常行われる葉の横断面の切片作成に加え、葉の裏面にある気孔観察の為の、表面を削る様に行う切片作成方法も指導しました。生徒は、実に熱心に参加し、生徒の意識の高さを伺うことができました。


午後は教員対象の学習会を実施しました。致遠館高校の教員三名ともう一人の教員が参加して、和気藹々とした雰囲気の中で実施できました。
ここでは、生物学オリンピックに向けた取り組みを私自身が行った経緯も紹介しました。教員として勤務した学校と、その中で実施した生物教育についてお話しし、現役最後に勤務した学校でのSPPの取り組み・オリンピックとの出会い・本選試験問題の作成・校内での特別教育の内容をお話しし、二人の日本代表生徒の指導についてもお話ししました。
国際生物学オリンピックに関しては、日本が参加してからの内容と、世界の生物教育のレベルが日本を上回っている事実についても説明しました。その中で我々教師がどの様にして実力を身に付けるかという事も説明しました。
よく知られている春の七草から、幾つかの設問を用意しました。先ずは七草の中に、日本に古くからあったのではなく、外国からもたらされた植物三種類についてお話ししました。スズナ・スズシロは容易に想像できますが、ナズナについては分かっていませんでした。生物の教科書でナズナが取り上げられるのは、胚の発生・同義遺伝が思いつきます。同義遺伝で説明される槍型の果実を日本で見た事のある人は、いても稀ですが教科書に記載されている事から当然あるはずです。日本で見られないのは、元々日本の植物ではないからです。教えている教師が、当然気付いて当たり前の事実を、気付くか気付かないかで、生態的な見方が出来るか出来ないかが分かれる事を理解して貰いました。
生徒対象・教員対象共に熱心に受講して頂き、充実した時間を過ごせた事に感謝します。
(文責 石井規雄)
ニュース, 国際生物学オリンピック, 日本生物学オリンピック
国際生物学オリンピック(IBO)は生物学に関心を持つ高校生等を対象とした国際的なコンテストです。若者たちに生物学の問題や実験に挑戦する場をあたえ、生物学への興味を喚起し、科学者への道に導くものです。さらに、生物学を学ぶ生徒どうしの国際的交流の機会をあたえ、生物学教育に関する問題の国際的な調査や意見交換も推進します。
国際生物学オリンピックの2020年国際大会を日本で開催するよう 昨2015年7月にデンマークのオーフスで開催された国際ジュリー会議において正式に承認されました。これを受けて 開催地などの検討を文部科学省はじめ関係する諸方面とともにすすめて来たところです。このたび、下記の要領で開催するよう準備することを決定しました。
日本において国際生物学オリンピック国際大会を開催するのは、2009年の筑波大会につぎ2回目となります。国際大会を複数回開催することは 規模の小さかった初期(第1,3回、チェコおよびスロバキア)を除けば、日本が初めてです。
国際大会の規模が前にもまして拡大していることなどを勘案して 開催地を長崎県としました。2020年には東京周辺において国際オリンピック・パラリンピックが開催され スポーツ競技を通して国際的な親善をはかることとされています。同じ時期に、科学する能力を国際的に競う場を日本が提供することは、科学・技術の健全な発達に日本が寄与し、人類文明の持続的発展への貢献をなすことで 日本の高い国際的な地位を築くことにつながります。長崎に全世界から生物学を志し将来指導的な立場にたつ若者と、それを育む教育関係者が多数集います。原子爆弾という20世紀の科学・技術のもたらした負の遺産に 国際生物学オリンピック参加者が長崎において近しく触れます。これは 科学と社会について深く思索を巡らすのに得難い契機を彼らに与えるものと期待されます。
国際生物学オリンピック2020国際大会開催の意義を理解いただき、その成功のために支援いただけますよう、心からお願い申し上げます。
記
- 会 期:2020年7月3日(金)~7月11日(土)(予定)
- 会 場:長崎国際大学(試験)およびハウステンポス(式典・会議および宿泊)
- 参加数(予測):70ヵ国・地域以上、代表生徒 約300名(各国4名まで)、各国ジュリー(審査・引率)約350名、運営スタッフ約150名(予定)
- 体 制:国際生物学オリンピック2020組織委員会、科学委員会、募金委員会、実行委員会
- 共催・後援など(予定):文部科学省、日本科学技術振興財団、長崎県、佐世保市、長崎国際大学
2016年3月20日(春分の日)午前9時より、東京工業大学西6号館2階の621号教室にて、「科学教育コンテストを活用した次世 代人材育成」と題したシンポジウムが行われた。
はじめに東京工科大学の毛塚博史氏による「物理チャレンジ教育活動と国際物理オリンピックへの日本参加」と題する講演があり、国際物理 学オリンピックに参加した経緯が紹介され、代表生徒を選考する側からの内容紹介として、物理チャレンジについての説明等があった。続い て、京都大学博士課程の植松祐輝氏による「物理チャレンジと物理教育 : 出場経験者としての視点から」と題する講演があり、物理チャレンジから、物理学オリンピックの専攻過程とその後の物理教育について紹介があった。
3人目にJBO教育支援部会の石井規雄が「国際生物学オリンピックに向けた学生指導の経緯から〜いかにして代表生徒を指導したか〜」と 題して、代表生徒を出す目標ではなく、研究者養成の通過点としての生徒指導の重要性を講演した。
4人目に福井県教育庁義務教育課の三崎光昭氏による「中学生のための理数探求イベント(ふくい理数グランプリ)」での中学生の生き生き とした取り組みについての講演があった。
最後にJSTの河崎泰介氏による「次世代人材育成における科学技術コンテストの役割」と題する講演があり、JSTが取り組んでいる「科学 の甲子園」などの紹介がされた。以上の5件が招待講演である。その他に会員発表として福井大学の葛生伸氏による「アドバイザーの立場から 見た高校生のための理数探求イベント(ふくい理数グランプリ)」と題して、高校生の取り組みについて紹介があった。
物理にとっては他の分野である生物学オリンピックが、どのような取り組みを行っているのかを知って頂く良い機会であった。 (文 責: JBO教育支援部会主査 石井規雄)

講演者の方々:写真の左から、毛塚博史氏、植松祐輝氏、石井規雄、三崎光昭氏、河崎泰介氏
新しい投稿ページへ古い投稿ページへ